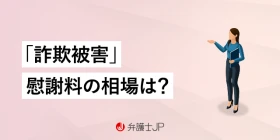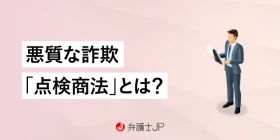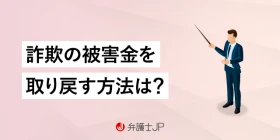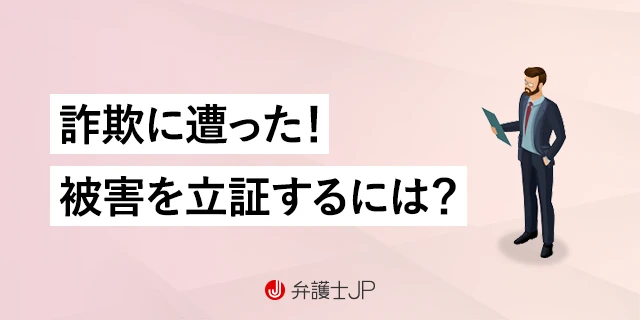
詐欺被害で犯人を訴えるには? 「刑事告訴」をするための要件と方法・手続き
詐欺事件の被害に遭ったら、犯人(加害者)の刑事告訴を検討しましょう。刑事告訴をすれば、犯人の訴追や示談金獲得の可能性が高まります。
本コラムでは、詐欺被害について刑事告訴をする(訴える)ことの意義や、詐欺被害の立証に役立つ証拠などについて解説します。
1. 詐欺罪とは|構成要件と法定刑
「詐欺罪」は、他人から財物または財産上の利益をだまし取る犯罪です(刑法第246条)。
金銭などの「財物」をだまし取る行為については「1項詐欺罪」(同条第1項)、代金の支払いを踏み倒すなどして「財産上の利益」をだまし取る行為については「2項詐欺罪」(同条第2項)が成立します。
(1)詐欺罪の構成要件
詐欺罪は、以下の構成要件をすべて満たす行為について成立します。
-
欺罔(ぎもう)行為
被害者をだます行為
-
錯誤
被害者の認識と事実が異なっている状態
-
交付行為
被害者が犯人に対して財物または財産上の利益が交付されたこと
-
財物または財産上の利益
被害者から犯人に財物または財産上の利益が移転したこと
-
因果関係
①~④の間に一連の因果関係があること
近年ではインターネット上を中心に、「投資詐欺」や「ロマンス詐欺」などさまざまな手口による詐欺が横行しています。
(2)詐欺罪の法定刑
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。刑法上の犯罪の中でも、詐欺罪は比較的重い部類の犯罪と言えます。被害額などによりますが、詐欺罪は初犯でも実刑となる可能性が十分考えられます。
2. 詐欺罪により刑事告訴をすることの意義
詐欺被害に遭ったら、刑事告訴を検討しましょう。刑事告訴をすると、犯人が訴追される可能性が高まるとともに、示談金を得られる可能性が生じます。
(1)犯人が訴追される可能性が高まる
詐欺被害者が刑事告訴をすると、捜査機関には詐欺罪について捜査を行う義務が生じます。
具体的には、捜査機関は以下の対応を行わなければなりません。
- 司法警察員(警察官)は、事件に関する書類および証拠物を、速やかに検察官へ送付する義務を負います(刑事訴訟法第242条)。
- 検察官が公訴を提起し、または提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知する義務を負います(同法第260条)。
- 検察官が公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人の請求を受けたときは、その理由を告訴人に対して告知しなければなりません(同法第261条)。
捜査機関によるこれらの対応は、犯人の訴追につながる可能性があります。また被害者としては、捜査の状況を知ることができるようになる点も刑事告訴の大きなメリットです。
(2)示談金を得られる可能性がある
刑事告訴によって犯人が訴追される可能性が高まると、犯人は被害者に対して示談を提案してくることがあります。示談が成立すれば、被疑者・被告人にとって良い情状として考慮され、重い刑事処分を避けられる可能性が高まるからです。
被害者としては、示談金の額が適正妥当であれば、示談に応じることも考えられます。刑事告訴を行い、犯人にとって刑事訴追のリスクが高まった状態を作ることは、示談交渉を有利に進めるための大きな材料となるでしょう。
なお、犯人との示談交渉以外にも、詐欺による被害金の返金を請求する方法はいくつか考えられます。詐欺被害に関する返金請求については、以下のコラムを併せてご参照ください。
3. 詐欺罪の被害を立証するには?
刑事手続きにおいて、詐欺罪の成立を立証する責任は検察官が負います。そのため、被害者が積極的に詐欺罪の成立を立証する必要はありません。
ただし刑事告訴の段階で、詐欺被害を受けた事実を客観的証拠により示すことができないと、警察は十分に捜査を行ってくれないケースが多いです。そのため、刑事告訴を行う前に、詐欺被害を立証しうる証拠を確保しておくことをおすすめします。
(1)詐欺罪の摘発率は約4割|立証のハードルは高い
令和5年版犯罪白書によると、令和4年度における詐欺罪の認知件数は3万7928件、摘発件数は1万6084件で、摘発率は42.4%でした。
出典:法務省「令和5年版犯罪白書」暴行・傷害・脅迫などの粗暴犯の摘発率が8割以上であることに比べると、詐欺罪の摘発率は5割未満と低く抑えられています。
その背景には、「被害者が犯人に対して自ら財物等を交付する」という詐欺罪の性質が関係していると思われます。
被害者が納得した上で財物等を交付したのか、それとも犯人にだまされて財物等を交付したのかは、被害者の内心の問題なので、他人には区別がしにくいケースが多いです。
捜査機関としては、「被害者がだまされた」ことを立証しなければならず、それが難しい場合には摘発できないという判断になってしまいます。
また、被疑者・被告人が詐欺の故意を否定するケースもあります。「だますつもりはなかった」と被疑者・被告人が主張した場合に、それを覆すだけの材料がなければ、やはり摘発見送りという判断になってしまうでしょう。
このように、詐欺罪の立証のハードルは比較的高いため、刑事告訴をする被害者の側でも、捜査機関に対して何らかの材料を提供することが求められます。
(2)詐欺罪の立証に役立つ証拠の具体例
詐欺被害者が刑事告訴をするにあたっては、詐欺被害を立証しうるものとして、以下のような証拠を捜査機関に提出するとよいでしょう。
-
犯人のだます行為や、被害者のだまされた状態が現れたメッセージ履歴、通話録音
-
詐欺について、犯人に対して追及した際のメッセージ履歴、通話録音
-
被害者が犯人の口座に対して振り込みを行った際の記録
など
これらの有力な証拠を豊富に提出することができれば、捜査機関が詳しい捜査に着手し、犯人が摘発される可能性が高まります。
4. 詐欺罪の刑事告訴・示談交渉は弁護士に相談を
詐欺罪を含む刑事事件について、刑事告訴や返金請求・損害賠償請求を検討している方は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、刑事告訴や返金請求・損害賠償請求に必要な手続きを全面的にサポートしてもらえます。特に詐欺罪については、「だまされたこと」の立証に多くの労力を要しますが、弁護士に依頼すれば効果的な立証の方法についてアドバイスを受けられます。
犯人と示談交渉を行う場合や、裁判所に訴訟を提起する際にも、弁護士のサポートを受けるのが安心です。弁護士に依頼すれば、法律のルールや過去の裁判例などを踏まえた請求を行い、適正額の示談金・損害賠償金を獲得できるように尽力してもらえます。
詐欺被害をできる限り回復するためには、弁護士への相談・依頼が大きな第一歩となります。詐欺罪による刑事告訴や、被害金の返金請求などについては、お早めに弁護士へご相談ください。

- こちらに掲載されている情報は、2024年10月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

犯罪・刑事事件に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年11月18日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年09月25日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年09月13日
- 犯罪・刑事事件