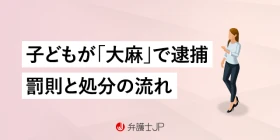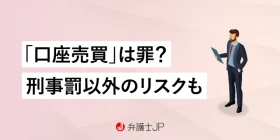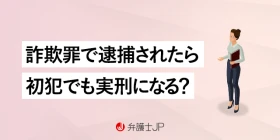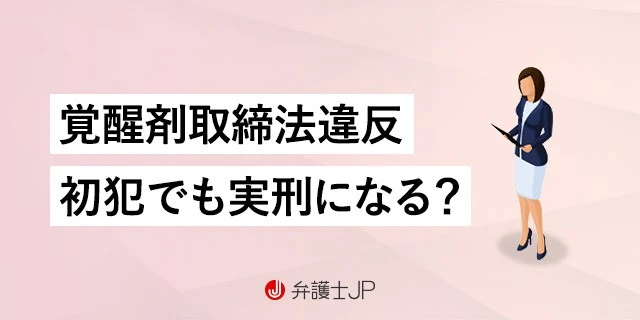
覚醒剤の初犯で逮捕された! 実刑になる可能性は?
覚醒剤取締法違反で逮捕・起訴された場合に量刑がどのくらいになるのかは、本人やご家族にとって非常に気になるところでしょう。
この記事では、違反行為ごとの法定刑や量刑、初犯の場合に実刑となる可能性があるかについてまとめています。また、逮捕後の流れについても簡潔に解説しています。
1. 覚醒剤取締法違反の法定刑と量刑
覚醒剤による逮捕とひとくちに言っても、覚醒剤取締法では複数の行為が禁止行為として定められており、どの行為をしたのかによって法定刑や量刑は異なります。法定刑とは各条文で規定された刑のこと、量刑とは法定刑にもとづき裁判所が決定した刑のことです。
以下、行為ごとに、法定刑と量刑についてみていきましょう。
(1)所持
覚醒剤の「所持」とは、覚醒剤を実際に管理している状態にあることです。覚醒剤を持ち歩いている場合だけでなく、自宅などに保管している場合や、誰かに預けている場合なども所持とみなされる可能性があります。
営利目的ではない覚醒剤の所持の法定刑は、10年以下の懲役です。一方で営利目的の場合は、1年以上の有期懲役が科されるうえに、情状により500万円以下の罰金も追加で科される可能性があります(覚醒剤取締法第41条の2)。未遂も処罰の対象です。
営利目的とは、他人に覚醒剤を売るなどしてお金を稼ぐことを指します。営利目的の場合、覚醒剤を社会に広げることになるため、量刑がより重くなります。所持の場合、営利目的かどうかのほかに、所持していた量なども量刑に影響します。
(2)使用
覚醒剤の「使用」とは、吸引や飲用など何かしらの方法で覚醒剤を使った場合のことです。自分自身に対して覚醒剤を使うだけでなく、他人に対し使った(注射したなど)場合も使用とみなされる可能性があります。なお、覚醒剤の使用が未遂(目的を達成していない状態)であっても、処罰の対象です。
営利目的でない覚醒剤の使用に対する法定刑は、10年以下の懲役です。一方で営利目的であれば、1年以上の有期懲役、または情状により500万円以下の罰金刑が併科されます(刑法第41条の3)。使用の場合、使用量や使用期間なども量刑に影響を与えます。
(3)譲受・譲渡
営利目的ではない覚醒剤の譲受・譲渡に対する法定刑は、10年以下の懲役です。一方で営利目的の場合は1年以上の有期懲役が科されるうえに、情状により500万円以下の罰金も追加で科される可能性があります(刑法第41条の2)。未遂も処罰の対象です。
譲受・譲渡は、社会への影響が大きいという点において、所持や使用よりも厳しい量刑になる場合があります。
(4)輸出入・製造
営利目的でない覚醒剤の輸出入・製造に対する法定刑は、1年以上の有期懲役です。一方で営利目的の場合は、無期か3年以上の懲役が科されるうえに、1000万円以下の罰金も追加で科される可能性があります(覚醒剤取締法第41条)。未遂も処罰の対象です。
輸出入・製造は、覚醒剤を広く流通させる行為のため、とくに重い刑罰が規定されており、営利目的の場合は最大で無期懲役という量刑もあり得ます。
2. 覚醒剤の初犯でも実刑になる?
覚醒剤取締法違反の罪で有罪となった場合、初犯であれば再犯に比べ量刑が軽くなる可能性があります。ただし初犯であっても、悪質であると認められて重い刑罰が科せられることは珍しくありません。
裁判官が悪質か否かを判断する要素としては、以下のようなものがあります。
- どのような経路で入手したか
- どのような事情や経緯で入手したか
- どのくらい使っているか、常習性が認められるか
- 営利目的であれば、重要な役割を担っていたか
- 本人が反省しているか、更生できる可能性が高いか
初犯であることに加えて悪質性が低いと判断されれば、執行猶予がつく可能性は十分にあります。一方、本人が主導で覚醒剤を販売していた場合や大量の覚醒剤を所持していた場合などは悪質性が高いとの判断に傾きやすく、実刑となる可能性も高まります。
実際の量刑は個別の事件によって異なりますが、初犯だからといって必ずしも執行猶予がつくとは限りません。不安であれば弁護士に相談するようにしましょう。
3. 覚醒剤で逮捕された場合の流れ
覚醒剤取締法違反で逮捕されたときに、どのような流れで刑事手続きが行われるかみていきましょう。
(1)逮捕
警察に逮捕された場合、留置場で身柄を拘束されたうえで、48時間以内に警察官からの取り調べを受けます。この間、薬物に関する証拠隠滅などを避けるため、家族などの外部とは一切連絡をとることはできない場合があります。その場合、逮捕された本人と連絡できるのは、担当の弁護人や、弁護人になろうとする者に限られます。
(2)送致
警察官の取り調べ後は検察庁へ身柄が移されます(送致)。検察官は、送致後24時間以内に取り調べを行い、起訴するのか、不起訴にするのか、それともさらに身柄を拘束して捜査を続けるべきかを判断します。
覚醒剤事件では、この段階で起訴・不起訴が決定することはほとんどありません。その場合、検察官による勾留請求が認められれば、最大で20日間の身柄拘束が続いた後、検察官が起訴するか否かを決定します(ただし、余罪で再逮捕されればその分身体拘束期間が延びることがあります)。
(3)起訴
検察官の判断で起訴された場合は、基本的には身柄が拘束され続けます。しかし保釈保証金を預ける前提で、起訴後に保釈を請求することも可能です。一方で不起訴処分となった場合は、その時点で釈放されます。
(4)刑事裁判
覚醒剤取締法違反の罪で起訴されると通常は約1~2か月後に刑事裁判が開始され、最終的に量刑が決定します。
1回目の刑事裁判で公訴事実や量刑などが争われなければ、その日のうちに審理を終結します(結審といいます)。単純な事件であれば、結審から2週間ほど後に判決を言い渡されるのが一般的です。ここで執行猶予がつけば、釈放され家に帰ることができます。
反対に実刑判決となれば、刑務所へ身柄が移されることになります。また1回目の公判期日で結審しない場合、おおむね1か月ごとに2回目、3回目の公判期日が開かれ、結審するまで続きます。
覚醒剤事件では、初犯の場合は執行猶予がつく可能性がありますが、不安に感じることが多いでしょう。少しでも不安をおさえ落ち着いて対応するためにも、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2023年08月02日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

犯罪・刑事事件に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年11月12日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年08月26日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年08月03日
- 犯罪・刑事事件