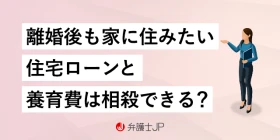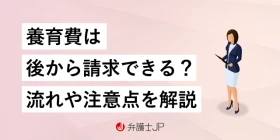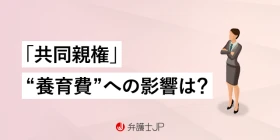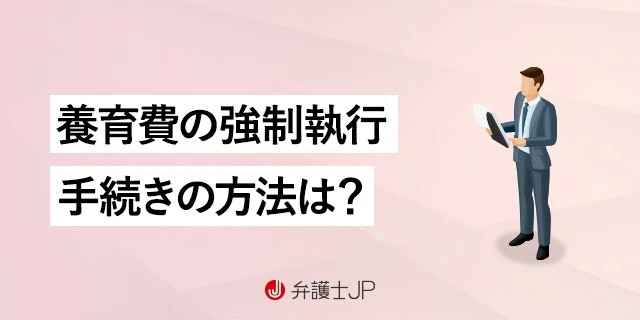
養育費の未払いは強制執行で解決? 強制執行ができる条件と手続きの流れ
子どもの養育費について「約束どおりに支払われない」「滞納されている」といったトラブルは決して少なくありません。
未払いの養育費の支払いを求める場合、まずは督促を行いますが、それでも支払ってくれない場合には「強制執行」という手段をとることが有効です。
本コラムでは、未払いの養育費を回収するための強制執行を行う条件やその流れについて解説します。
1. 養育費の強制執行ができる条件とは?
強制執行とは、借金が返済されないなど約束(債務)が守られないときに、国が財産を差し押さえるなどして、強制的に約束を守らせる法的手続きのことです。
相手が養育費を支払ってくれない場合には、この強制執行によって相手の財産を差し押さえることができます。
(1)対象となる財産
対象となる財産は以下のとおりです。
- 不動産:土地、建物など
- 動産:現金、家具家電、商品など
- 債権:預金、給料、売掛金など
(2)債務名義の取得
強制執行をするためには、「債務名義」を取得していることが必要になります。債務名義とは、債権の存在やその範囲を公的に証明する文書のことをいい、養育費の場合には、『毎月○万円の養育費の支払い義務がある』ことを公的に認めた文書を指します。
債務名義になるものは公的な証明文書に限られます。したがって、離婚協議書に養育費の支払いについての事項が記載されていたとしても、それは債務名義にはなりません。
債務名義となるのは次のものが挙げられます。「執行文」とは強制執行を認める文言です。
-
①「執行文の付与」が不要な債務名義
- 家事調停調書正本
- 仮執行宣言付支払督促正本
- 家事審判書正本
-
②「執行文の付与」が必要な債務名義
- 判決正本
- 和解調書正本
- 民事調停書正本
- 公正証書正本
「執行文の付与」がない場合は裁判所や公証人に依頼する必要があります。
協議離婚の場合、「執行認諾文言付き公正証書」を作成していれば、それがそのまま債務名義になります。しかし、公正証書を作成していなかった場合には、債務名義に該当するものがありませんので、改めて養育費請求調停を申し立てるなどして債務名義を取得しなければなりません。
離婚調停や離婚裁判によって離婚をした場合には「調停調書」や「判決書」が交付されているはずですので、それが債務名義になります。
(3)相手の財産の把握
強制執行を行うには、相手方の財産を特定しなければなりません。つまり、どこにどのような財産があるかを具体的に把握する必要があります。
未払いの養育費に関しての強制執行は、主に相手方の預貯金や給料を対象にして行うことが多いため、相手方の預貯金口座がある金融機関と支店、相手方の勤務先といった情報が必要になります。
離婚前に把握できていればベストですが、離婚後でも相手を裁判所に呼び出して財産について聞きとりをする「財産開示手続き」などにより調査できます。また、弁護士に調査してもらうこともできます。
なお、以前は強制執行できる債務名義の種類が限られていたり、相手の財産がわからなかったりして、未払いがあっても泣き寝入りしてしまう方が少なくありませんでした。
そこで、2020年4月、強制執行などについて定めた民事執行法が改正・施行され、以下のような変更が加えられました。
- 強制執行を行える債務名義の種類拡大
- 財産開示手続きに相手が協力しない場合の罰則強化
- 市町村など第三者からの財産情報取得手続きの新設
この改正により強制執行がしやすくなると期待されています。
養育費の未払いでお困りの方は、弁護士などのサポートを受けながら強制執行を進めて養育費を確保しましょう。
2. 養育費の強制執行をする流れ
債務名義を取得して、相手の財産を把握している場合には、強制執行の申し立てを行います。養育費の強制執行をする場合の手続きと流れについては、次のとおりです。
(1)強制執行に必要な書類と手数料
強制執行の申し立ては、次の書類と手数料を相手方の住所地を管轄する裁判所に提出する必要があります。
-
必要書類
- 申立書(表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)
- 債務名義の正本
- 送達証明書
- その他の書類(戸籍謄本、住民票、戸籍の附票など)
-
手数料
4000円
収入印紙で用意します。債権者と債務者が1名ずつで債務名義1通の場合は、4000円です。
-
郵便切手
郵便切手の金額については、裁判所によって異なりますので、申し立てをする裁判所に確認してみましょう。
(2)申し立て後の流れ
-
申し立て受理
申立書類に不備がなければ、申し立てが受理されます。
-
差押命令
申し立てが受理されると、裁判所から債務者、第三債務者に対して、債権差押命令が送達されます。第三債務者(金融機関など)に差押命令が届いた時点で、債務者の銀行口座は停止され、出金をすることができなくなります。
-
取立て
債務者に差押命令が送達された日から1週間経過後に、債権者は債権を取り立てることが可能になります。支払い方法などについては、債務者の職場や金融機関に直接連絡をして相談するようにしましょう。取立てが完了した場合は、裁判所に対して取立完了届を提出し、養育費の差押さえは終了です。
このように、養育費の未払いがある場合には、強制執行の手続きをとることによって履行を確保することが有効です。
最もハードルが高く感じられるのは、相手方の財産状況を把握することと、確実に差し押さえることかも知れませんが、近年の制度改正により、強制執行という手段の実効性が高められてきています。
養育費の不払いでお困りの方は、ぜひ、弁護士などのサポートを受けながら強制執行を進めることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2025年01月10日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年12月06日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年11月29日
- 離婚・男女問題