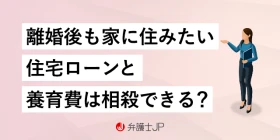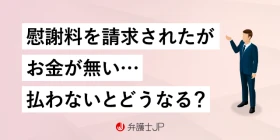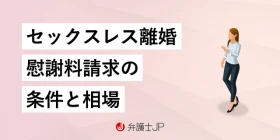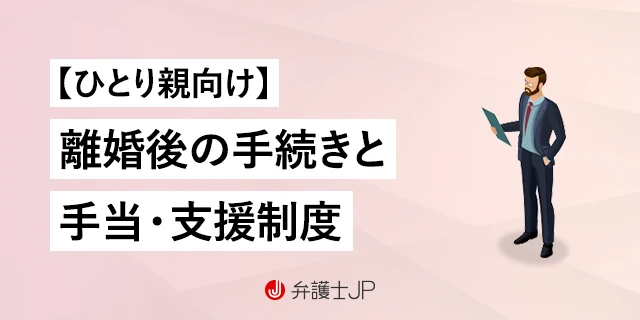
シングルマザーの離婚後に必要な手続き|受けられる手当や支援も紹介
婚してシングルマザーとなったら、母子ともに新生活を始めるにあたって、子どもの姓に関するものなどさまざまな手続きが必要となります。
本コラムでは、公的書類や戸籍などに関係する手続きをはじめ、財産分与や養育費、慰謝料などの元配偶者に請求できるお金、受けられる可能性のある手当・支援などを解説します。
1. 離婚後にシングルマザーがやるべき手続き
離婚後は、次に挙げる手続きをなるべく速やかに行いましょう。
(1)公的書類・戸籍に関するもの
役所関係の手続きです。まとめて1日で手続きした方が負担は少ないので、あらかじめ管轄の役所に尋ねた上で、必要な書類を全てそろえておくことをおすすめします。
①姓の変更
婚姻期間に元配偶者の名字を名乗っていた場合、離婚届を提出すると自動で旧姓に戻ります。元配偶者の名字を使い続ける場合は、離婚3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、新しい戸籍を作らなければいけません。本籍地以外で届け出するには、戸籍謄本が必要です。
②公的身分証明書の手続き
運転免許証をはじめ、パスポートやマイナンバーカードといった公的身分証明書の手続きも行いましょう。運転免許証の変更は引っ越し先を管轄する警察署か運転免許センターで行います。パスポートは旅券申請窓口、マイナンバーカードは市区町村の役所で変更できます。
③引っ越し関係の手続き
離婚後に引っ越しをする場合、引っ越し日から14日以内に転居届などを提出します。同じ市区町村なら転居届だけで問題ありませんが、別の市区町村に引っ越す場合は、「転入/転出」の届け出が必要です。これまで住んでいた市区町村で転出届を提出して「転出証明書」を発行してもらい、転居後、引っ越し先の市区町村で「転入届」を提出しましょう。
なお、2023年から、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルを通じて転出届の提出が可能になりました。
(2)子どもに関するもの
子どもの戸籍に関する手続きなども、なるべく早く行いましょう。
①子どもの姓に関する手続き
親が旧姓になっても、子どもの名字は変わりません。子どもの名字を旧姓にあわせて自分の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、さらに市区町村に「入籍届」を提出しましょう。その際は、子の氏の変更許可審判書と戸籍謄本が必要です。
②保育園・幼稚園、学校、学童などへの報告
子どもが通っている保育園・幼稚園、児童発達支援や放課後等デイサービス、学校、学童などへも離婚をした旨の報告を行いましょう。子どもが今後名乗る姓を伝え、必要があれば諸費用の引き落とし口座や緊急連絡先も変更します。転園・転校、学童への入所・変更などを行う場合は、自治体によって手続き内容や手順が異なるため、引っ越し先の市区町村の役所にあらかじめ確認しておくとスムーズです。
③児童手当の受給者変更手続き
児童手当の振込先が元配偶者である場合は、役所で受給者の変更手続きを行い、新たに受給者認定を受ける必要があります。
(3)健康保険や年金に関するもの
元配偶者の扶養に入っていた場合は、新たに国民年金と国民健康保険の加入手続きも必要です。市区町村の役所で行います。
2. 離婚後に相手から支払われるお金
離婚するにあたり、以下のようなお金を相手から受け取ることが可能です。いずれも当事者間の話し合いで決められますが、家庭裁判所で話し合うことも可能です。弁護士に相談することも有効です。
(1)養育費
親は未成年の子どもに、自分と同じ水準の生活を保障しなければいけません。そのため、子どもを引き取らない側は、離婚に伴って子どもの生活水準が著しく下がらないように、自分が本来養うべき分の養育費を支払う義務があります。養育費の適正額や期間は、それぞれの年収や子どもの年齢・人数、子どもの障害の有無などで異なります。
不払いが起こらないよう、場合によっては法的な強制執行力のある「強制執行認諾文言(約款)付公正証書」を作成します。
(2)財産分与
元夫婦どちらに離婚原因があったとしても、結婚していた期間に築いた夫婦の共有財産から「財産分与」として50%相当額を請求できます。預貯金や持ち家、車、有価証券などが財産に含まれます。元配偶者名義の預貯金なども該当しますが、相続で得た財産など、夫婦の協力とは無関係なものは対象外です。なお、住宅ローンや教育ローンなど、夫婦共同の負債も分担しなければなりません。
日本年金機構に申し出れば、厚生年金保険料を分割し、将来の年金額に加算される「年金分割」も可能です。また、夫婦どちらかの病気や育児などで経済力がない場合、一定の期間、生活費の補助としてお金を支払う「扶養的財産分与」もあります。
(3)慰謝料
相手の不倫やDV(身体的・経済的を含む)・モラハラ、セックスレスなどが離婚原因であれば、肉体的・精神的な苦痛を受けたことに対して慰謝料を請求できます。性格の不一致などは判断が難しく、責任の割合によって金額が決定します。また、生活費が支払われず結婚前の貯金などを切り崩していた場合などは、本来の元配偶者が負担すべきだった分を請求できるので、証拠をそろえておくことが大切です。
3. シングルマザーが離婚後に受けられる手当・支援
シングルマザーになったら、次のような手当や支援が受けられることがあります。
(1)手当・助成金の例
①児童扶養手当
所得や子どもの人数によって金額は変わります。全部支給だと月額4万4140円、一部支給で1万410円~4万4130円です(令和5年4月時点)。子どもが2人以上いる場合は、さらに加算されます。18歳になる年の3月31日まで、奇数月に支払われます。
参照:男女共同参画局「児童扶養手当」②住宅手当
市区町村によっては、未成年の子どもを養育するひとり親世帯に住宅手当が支払われる場合もあります。たとえば埼玉県蕨市では、民間の賃貸住宅に入居しているシングルマザーに対して、一定の条件を満たせば6000円~1万円が支給されます。
参照:蕨市「ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成」(2)支援の例
①国民保険・国民年金の免除
国民健康保険は、シングルマザーに限らず、前年の所得が一定の基準以下の世帯は、保険料が軽減されます。同じく国民年金も、保険料の納付が難しければ、全額免除や減免、納付猶予の制度があります。ただし、将来受け取る年金額が減ってしまうため、経済的に余裕が生まれたら追納するのがおすすめです。
②公共交通機関の割引
市区町村によっては、公共交通機関の割引を受けられることもあります。たとえば東京都では、児童扶養手当を受けている世帯の人は、JRの通勤定期券を3割引で購入できます。また、世帯の構成員のひとりのみ都電や都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人(とねり)ライナーの一定区間の無料乗車券が交付されます。
各市町村によって受けられる手当・助成などは大きく異なります。そのため詳しい内容については、お住まいの自治体のホームページで必ず確認するようにしてください。なお、所得制限があるものや自分自身で申請を行わないと受け取れない支援、支給までに時間がかかるものもあるため、注意が必要です。
さまざまな手続きを進めなければなりませんが、母子ともに心機一転、新たな生活を迎える準備だと思って、ひとつずつこなしていきましょう。必要に応じて養育費や慰謝料などの交渉を弁護士に任せるのも、より円滑に進める一手です。受けられる支援を活用しつつ新生活をスタートさせてください。

- こちらに掲載されている情報は、2024年05月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新2025年版 養育費計算ツール
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2025年01月10日
- 離婚・男女問題
-
- 2025年01月08日
- 離婚・男女問題
-
- 2025年01月07日
- 離婚・男女問題