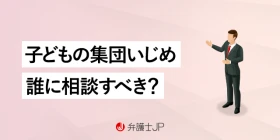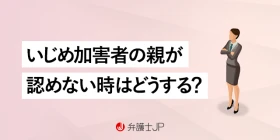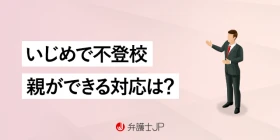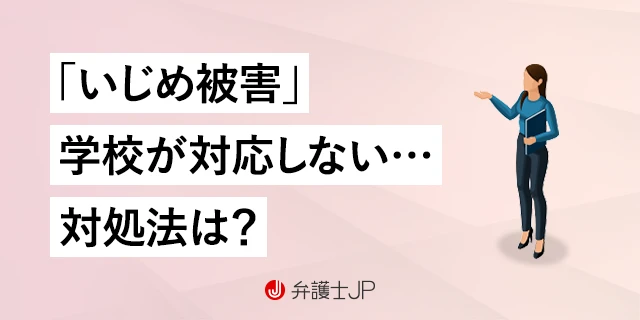
学校がいじめを隠蔽? 子どもを守るための対処法や相談先について解説
子どもがいじめを受けているのに、学校が頼りにならないばかりか、むしろいじめを隠蔽しようとしている。そのような状況は親にとって非常に不安の大きいものです。
本コラムでは、いじめ問題に学校が対処してくれない場合の相談先として、教育委員会や文部科学省、弁護士といった学校外の窓口について解説します。
1. 子どもがいじめを受けているときの兆候
いじめ被害を受けている子どもは多くの場合、親に相談できず、1人で悩みを抱え込みがちです。それには「親に心配をかけたくないから」「親に告げ口をしたと知られるといじめが悪化するから」など、さまざまな理由がありますが、いずれもいじめの隠蔽性を高める結果を生み出しています。
そのため、親としては子どもが直接相談してくれなくても、普段の行動や態度の変化からいじめの兆候を察知することが重要です。
子どもがいじめを受けているときの兆候としては、たとえば以下の変化が挙げられます。
- 学校に行きたがらなくなる
- 学校や友達の話題を避ける
- 朝起きられなくなる
- 食欲がなくなる
- スマートフォンの着信音におびえたり、神経質にチェックしたりする
- 友達と遊ぶことが減り、部屋に閉じこもる時間が増える
- 勉強に集中できなくなり、成績が落ちる
- 服や靴、学用品がなくなったり、壊れたりしている
- けがをしているにもかかわらず、その理由を言いたがらない
(参考:「ここにもあります!相談できる窓口が。「いじめ」しない させない 見逃さない」(政府広報オンライン))
もちろん、これらの兆候が必ず学校のいじめと関係しているとは限りません。しかし、たとえいじめではないとしても、こうした兆候は、子どもの体や心、置かれている状況に何らかの変調が出ている可能性が高いことを示唆しています。
そのため、親としては日頃から子どもの様子を気にかけ、異常が確認された場合はすばやく相談に乗ったり、フォローをしたりできるようにすることが求められます。
2. 教師や学校が対応してくれない場合
子どもが学校でいじめ被害を受けていた場合、親が最初に相談する先は、やはり担任教師です。もし担任教師が適切な対応をしてくれないときは、教頭や校長といった、より立場が上の教員に相談することで事態が改善する可能性があります。いじめ被害を大ごとにすることを、子ども自身が望まないケースも多いので、まずは学校内での解決を目指しましょう。
しかし、それでも学校が対応してくれない場合、次は教育委員会に相談することも検討しましょう。
(1)教育委員会の役割と相談プロセス
教育委員会は、地方公共団体が設置する教育に関する行政機関で、都道府県・市区町村ごとに存在します。教育委員会の役割は、簡単に言うと、地域の教育体制を適切に管理・監督することです。そのため、教育委員会は公立学校に対して強い権限を持っており、各学校が自治体の定めた規定や学校教育法などに違反した場合、対応を改めるように命じることができます。
教育委員会への相談は、まずは電話やメールで事情を連絡し、その後、該当校区の担当者と面談するのが一般的な流れです。いじめの場合なら、教育委員会から校長を経由して、事実関係の調査や生徒指導の改善、被害児童のメンタルヘルスケアなどの介入が期待できます。
(2)教育委員会に相談してもいじめ問題が解決するとは限らない
ただし、教育委員会への相談が常にいじめ問題の解決に結びつくとは限りません。そもそも教育委員会の原則的な立場は、学校や保護者に対して「中立」です。教育委員会としては、過度に各学校現場へ干渉しないように、学校への強い処分を避ける傾向があります。
特に、以下のように被害や影響が目立たない場合は、その傾向が顕著です。
- いじめ被害の証拠がない
- 長期的な不登校などの明らかな影響が出ていない
- 暴力やわいせつなどの事件性までは見受けられない
過去には、教育委員会が学校と結託していじめを隠蔽した悪質なケースも報道されています。
また、公立学校に対しては強い権限を持つ教育委員会も、私立学校の教育に対しては介入する強い権限を持っていません。したがって、子どもが私立学校に通っている場合は、その学校法人の理事長や母体団体などへ訴えたほうが適切です。
3. 教育委員会に相談しても解決しないときは
(1)いじめ問題に対する政府系の相談先
教育委員会が頼りにならない場合でも、いじめ問題の相談先は他にもあるので諦めないでください。たとえば、文部科学省が設置した「子供のSOSの相談窓口」、法務省が設置した「こどもの人権110番」などがその代表例です。
①子供のSOSの相談窓口
相談の手段として、SNS・電話・地元の相談窓口という3つが紹介されています。
(参考:「子供のSOSの相談窓口」(文部科学省))
②こどもの人権110番
子どものSOSに対して相談を受け付ける専用相談電話です。メールやLINEでの相談もできます。
(参考:「いじめ などの電話相談窓口【こどもの人権110番】」(法務省))
こうした窓口に相談することで、いじめ問題への対処について適切な助言やサポートを得ることが可能です。匿名やSNSでの相談も受け付けているので、学校や教育委員会にいきなり相談するのが不安な場合は、ここでいったん話を聞いてもらうことも検討しましょう。
(2)弁護士への相談も有効
いじめに事件性がある場合や、学校側が対応してくれない場合は、弁護士へ相談することも有効な手段です。いじめ行為の中には暴行・恐喝・窃盗など犯罪に該当するものもあり、これらに対しては刑事告訴を行えるほか、心身への被害が生じていれば損害賠償請求もできます。
また、学校や教育委員会がいじめの事実を放置・隠蔽した場合は、安全配慮義務違反にあたるので、学校側に損害賠償請求をすることも可能です。弁護士に相談すれば、このように法的な観点から相手の責任をスムーズに追及できます。弁護士が介入することにより、こちらの本気度やいじめの罪深さについて、加害者や学校の認識が改まることも期待できます。
本コラムで紹介したように、いじめ問題の相談先は、学校が対応してくれない場合は教育委員会、教育委員会が対応してくれない場合は他の相談窓口や弁護士というように、数多く存在します。自殺などの最悪の事態に至らないように、保護者は子どもの様子を気にかけ、必要とあればためらわずにこうした相談先を利用しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年03月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

学校問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月28日
- 学校問題
-
- 2024年06月26日
- 学校問題
-
- 2024年06月02日
- 学校問題