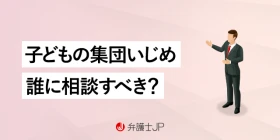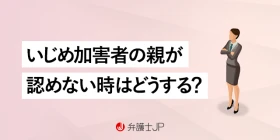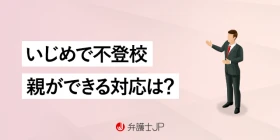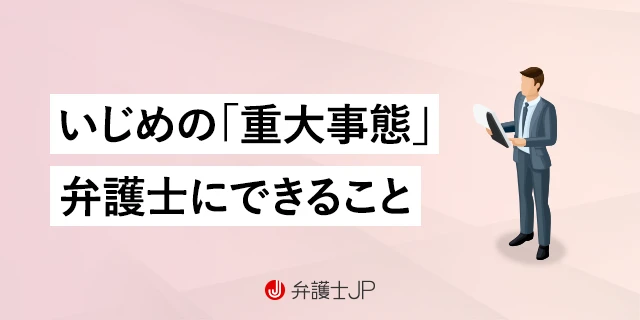
いじめの重大事態とは? 弁護士にできることと法的対処を解説
学校で行われるいじめのうち、一定のものは「重大事態」として法律に定められています。子どものいじめ被害が深刻なものと見られるのであれば、弁護士による支援を受けて加害者や学校と話し合うことが大切です。
本コラムでは、いじめの重大事態について解説します。
1. いじめの「重大事態」とは?
(1)法律上における「重大事態」の定義
学校側がいじめの防止対策や実態調査を行う際には、その必要性をまず判断しなければなりません。そこで学校が適切に判断できる基準として、いじめ防止対策推進法(いじめ防止法)第28条第1項で、次のとおり、いじめの「重大事態」というものが定められています。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
いじめ防止対策推進法 第28条第1項
要約すると、いじめを原因とする「生命や心身、財産の被害」が生じ、あるいは「相当期間の欠席状態」を余儀なくされていると疑われる場合に、重大事態が起きていると判断されます。
(2)重大事態と判断されるケース
文部科学省の資料によれば、各教育委員会などにおいて重大事態と判断された事例には、以下のものが挙げられます。
- 自ら命を絶とうとした
- 自傷行為(リストカットなど)を行った
- 殴られて骨折した、歯が折れた
- 人前で服を脱がされ裸にされた
- 金銭を強要され1万円を渡した
- 欠席が続き退学や転学をした
出典:文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」
なお、重大事態の目安となる欠席日数は年間30日です。ただし、その日数に達していなくても重大事態に該当すると判断される可能性はあります。
(3)重大事態に際して学校などに義務づけられた対応
いじめの被害を受けた児童などが重大事態に該当すると判断された場合、学校などにはいくつかの対応が義務づけられます。主な対応として挙げられるのは、①報告、②調査組織の設置、③調査、④対処・防止措置の4点です。
①報告
学校は、重大事態が発生したことを行政機関などへ報告します。また、後述する③の調査後には、その結果も報告する必要があります。報告の主体と報告先は、以下のとおりです。
- 国立学校→文部科学大臣
- 公立学校→当該地方公共団体の長
- 私立学校→所轄の都道府県知事
- 学校設置会社が設置する学校→認定地方公共団体の長
②調査組織の設置
学校は、重大事態が起きたと判断した場合、その下に調査組織(第三者委員会)を速やかに設けます。組織の構成員には、弁護士や精神科医、スクールカウンセラーなど、専門的知識・経験を有する者が挙げられます。この構成員は、調査の公平性・中立性を確保するため、当該いじめ事案と人間関係や利害関係を有さない第三者であることが必要です。
③調査
事実関係を明確にすべく、いじめ調査を実施します。事実関係とは、いじめがいつ、誰から、どのように行われたか、その背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があり、学校はどのような対応をしたか、といった事柄です。
④対処・防止措置
学校は、調査結果を児童生徒とその保護者へ情報提供し、1.~4.に報告します。その後、報告を受けた文部科学大臣などは、必要に応じて再調査を行います。調査結果を踏まえて、学校など(教育委員会や首長部局などを含む)は対処・防止措置をとらなければなりません。
【必要な措置の例】
- 指導主事や教育センターの専門家を派遣し、重点的な支援を行う
- 専任として生徒指導に取り組む教職員の配置など、人的体制を強化する
- スクールカウンセラーや教員・警察官経験者など、外部の専門家を追加配置する
2. いじめの重大事態に対し弁護士にできること
(1)学校が対応を怠ったケース
先述のとおり、学校には重大事態に対するいくつかの義務があります。しかし、学校が調査・対処を怠るケースも見られるのが実情です。
実際に、令和3年末から翌年にかけて、兵庫県芦屋市内の小学生が同級生からいじめを受けて49日間欠席する事態が生じました。本件では重大事態の認定まで7か月かかり、その児童は転校を余儀なくされています。
他にも、令和2年に東京都品川区で発生した事例では、教育委員会が区立中学生に対するいじめの事実を把握していながら、重大事態の認定まで2年以上かかるという問題が起きました。被害を受けた生徒は適応障害と診断されて転校しています。
(2)主な法的対処方法と弁護士にできること
こうしたいじめ問題では、民事・刑事の両面で加害者に対する責任追及が可能です。学校側が対応してくれない場合や、重大事態として認めてくれない場合、とれる法的手段としては以下の2つが考えられます。
- 加害者や学校への損害賠償請求(民事)
- 加害者の刑事告訴(刑事)
まず民事では、加害者に対し慰謝料や治療費といった損害の賠償請求が可能です。また、学校に対しても安全配慮義務違反などを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。この場合、弁護士としては、適切な慰謝料相場のアドバイスや加害者・学校との交渉、事実関係調査のサポートなどができます。
次に刑事では、加害者の刑事告訴が可能です。この場合、弁護士としては被害者の代理人として警察へ被害届を出す、被害の裏づけとなる資料を添えて告訴を行うことができます。
3. 子どもが重大事態にあたるいじめを受けていたら
保護者として、子どもがいじめを受けていると知った場合には、その子どもがどうしたいか(転校したい、休学したいなど)の意思確認や、精神面のケアを行う必要があります。その際には、まず自身が子どもの味方であることをきちんと伝えましょう。
また、学校に適切な対処やいじめの再発防止策を求めることも有効です。感情的にならず、あくまでもいじめ問題の解決を主眼に置いた話し合いをしなければなりません。
これらに加えて、弁護士への相談も検討する余地があります。とりわけ、加害者や学校がいじめの事実などを認めなかった場合、交渉や訴訟において弁護士は心強い味方となります。このとき、いじめの証拠を残しておくことが重要です。たとえば、暴行によるけがの診断書や、いじめ現場の写真・動画、友人の証言、壊された物品などが挙げられます。
いじめの重大事態に対処するには、加害者や学校との交渉、訴訟提起が必要になることがあります。こうした手続きや重大事態調査などを円滑に行うには、弁護士への相談を検討しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

学校問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月28日
- 学校問題
-
- 2024年06月26日
- 学校問題
-
- 2024年06月02日
- 学校問題