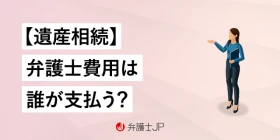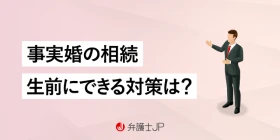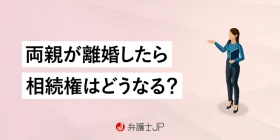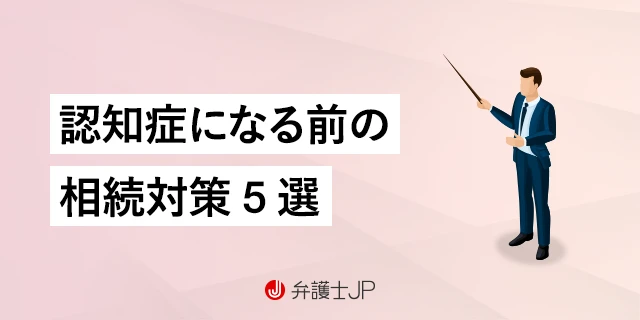
被相続人が認知症|遺産相続はどうしたらいい? 問題点や相続対策を解説
認知症になると判断能力が低下するため有効な相続対策をするのは難しくなります。将来的な遺産相続に備え、十分な判断能力があるうちにできる対策をしておきましょう。
本コラムでは、認知症になることで生じる法律行為への影響と認知症になる前の対策を解説します。
1. 認知症の人の相続対策はできない?
法律上、正常な意思能力がない状態で行った法律行為は無効とされます。
意思能力とは、その行為の結果としてどんな権利や義務が発生するのかを判断できるだけの能力のことです。意思能力の有無や程度は医学的な観点を含めて個別に確認されますが、認知症の場合は意思能力がないと判断される可能性が高く、以下のようなさまざまな法律行為ができなくなります。
自分の死後、遺された家族が相続を円滑に進めるために、生前贈与や遺言の作成、不動産の売却などの相続対策を検討している方は多いでしょう。しかし、上記のように、認知症になると相続に関する行為も制限されるため、有効な相続対策を講じることが困難です。
2. 認知症の被相続人の遺言はどうなる?
遺言は、遺言者が自分の財産に関して行う意思表示です。遺言は相続においてもっとも優先されるため、誰に何をどれくらい相続させるのかを被相続人の意思で決めることができます。しかし、認知症の被相続人が作成した遺言については、後々トラブルに発展することが少なくありません。
(1)認知症の被相続人が作成した遺言は無効になる
遺言は、その内容や法的効果を理解して自分で判断できる能力が必要な法律行為です。そのため、認知症の被相続人が作成した遺言は無効と判断されることが多くあります。
もっとも、認知症の進行状況は人によって違いがあるため、認知症の被相続人がした遺言がただちに無効になるわけではありません。意思能力の程度だけでなく、遺言の内容(単純な内容か、複雑な判断を要するかなど)によっても、遺言が有効だと認められることはあります。
しかし、医師から認知症と診断されたあとに作成した遺言は、「遺言作成時に正常な判断能力を欠いていた」として、相続人によってその有効性が争われることが珍しくありません。その場合の最終的な判断は裁判所が行いますが、係争中は相続が進まないのに加え、相続人同士の関係性が悪化しかねないでしょう。
したがって、認知症の被相続人が作成した遺言は、あとになってトラブルに発展するリスクがあると知っておく必要があります。
(2)成年後見制度は相続対策にはならない
認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった方の意思決定を支援する制度として、成年後見制度(法定後見制度)があります。
正しい判断ができないことで本人が不利益を受けないように、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって法律行為をしたり、本人がした法律行為の同意や取り消しをしたりできる制度です。
相続の場面において、成年後見人は遺産分割協議へ参加することや的確な主張によって本人の法定相続分を守ることなどができます。しかし、成年後見人の主な役割はあくまでも本人の財産を保護することです。そのため本人に不利益が発生する可能性がある相続対策は原則としてできません。
たとえば相続対策として、基礎控除内の生前贈与を行い、相続人が贈与税を支払わないで済むようにする方法があります。しかしこれは相続人の利益にはなっても、被相続人の財産を減らしてしまう行為なので、成年後見人が行うことはできません。
ほかにも、アパートを建てたり売却時の価値を高めるために自宅のリフォームをしたりといった相続対策も、被相続人の財産を減らすおそれがあるため困難です。
このように、成年後見制度は、相続対策としては必ずしも有効ではありません。
3. 被相続人が認知症になる前にとれる対策とは
上記のように、認知症になってから相続対策をすることは非常に困難です。何の対策もできないまま自分が亡くなり、遺された家族が相続のことで困ったりもめたりするのは、被相続人も本意ではないでしょう。しかし、被相続人が認知症になる前、あるいは軽度の認知症なら、とれる対策が複数あります。
(1)任意後見制度を活用する
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに任意後見人を選任し、財産管理や療養看護に関する事務などについて代理権を与える制度です。
任意後見契約は判断能力がある人しか締結できませんが、契約の効力は判断能力が低下したあとに発生します。つまり、事前に任意後見契約を結ぶことで、将来的に認知症になった場合に備えることが可能です。
任意後見制度は成年後見制度(法定後見制度)とは異なり自分で後見人を選べるため、自分が信頼する人に将来の財産の管理などを任せることができます。また、ある程度自由度が高い契約なので、依頼したい内容や権限の範囲、財産の管理方法などを公正証書による契約で取り決めることが可能です。
(2)家族信託で対策する
家族信託は、財産の管理や処分を家族に委託できる仕組みです。任意後見制度と同様に判断能力があるうちに契約する必要がありますが、認知症になったあとにも継続して利用できます。
この仕組みは、「委託者」「受託者」「受益者」の三者からなります。委託者と受益者は兼ねることができるため、財産を所有する親(委託者)が子どもなどの信頼できる家族(受託者)に財産を託し、その財産から発生した利益は親である本人(受益者)が受け取るケースが一般的です。
前述した任意後見制度は、後見人として適正に役割を果たしているかを任意後見監督人や家庭裁判所に報告する必要があるため、後見人になった家族には一定の負担がともないます。一方、家族信託はこのような監督を受けません。
また、本人の財産を減らさないことが重視される成年後見制度と異なり、財産の売却や投資運用など、契約の内容にしたがって受託者が柔軟に財産を管理・処分できます。
(3)生前贈与をしておく
生前贈与は、被相続人が存命のあいだに、指定した相手に財産を与える制度です。通常、贈与を受けた人は贈与税を納める必要がありますが、1年間に贈与された財産の合計が110万円の基礎控除額以下なら贈与税はかかりません。そのため税負担を抑えたいときの相続対策としてよく利用されている制度です。
生前贈与は意思能力が必要な法律行為なので、認知症になったあとにしても無効になるおそれがあります。しかし認知症になる前なら、自分が財産を与えたい相手に贈与できます。法定相続人のように財産を引き継ぐ人が決まっているわけではありません。
ただし、基礎控除額を超えた生前贈与については贈与税が発生するため、贈与する財産の金額には注意が必要です。
(4)公正証書遺言を作成する
認知症になる前に遺言を作成しておけば、認知症になったあとに亡くなっても、被相続人の意思にもとづき財産を引き継いでもらえます。とくに、公正証書遺言は信用力の高い遺言を作成できるため、遺言の内容を確実に実行したい場合に推奨します。
公正証書遺言は、法律知識と実務経験を有する公証人が、公証役場において公証人と証人2名の立ち会いのもと作成する遺言です。作成当日は、遺言者本人が公証人に対して遺言の内容を口頭で告げ、公証人は遺言者の真意であることを確認した上で作成します。
公証人が目の前で遺言者の言動を確認していることから、そのときに遺言能力があったことは一定程度担保されます。相続人による「遺言時に認知症だったのだから無効ではないか?」といった主張を防ぎやすくなります。
また、遺言の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんなどのおそれもありません。家庭裁判所の検認手続きを経る必要もないため、亡くなったあと速やかに遺言の内容を実行してもらえます。
(5)委任契約を結ぶ
委任契約(財産管理委任契約)とは、委託者(本人)に判断能力があるうちに、受託者(家族や第三者)に財産の管理を委任する契約のことです。たとえば金融機関での手続きや税金・保険料の支払い、不動産の売却手続きなどを代行してもらうことができます。
委任契約を結んでおけば委任状や印鑑証明書などを手続きの都度用意する必要がないため、手続き関係を家族などに任せたい場合に便利です。
委任契約は家族信託と似た仕組みですが、家族信託は本人の判断能力が低下しても継続できるのに対し、委任契約は本人の判断能力がないと使えません。
認知症になったあとは本人の意思確認ができないため、たとえ委任契約を結んでいたとしても受託者は財産の管理や処分ができなくなります。そのため、委任契約は切れ目なく財産の管理を任せられるよう、任意後見制度とセットで利用されることが多い仕組みです。
認知症になる前から行える相続対策としてどの方法が適しているのかは、自分や家族の状況によって異なります。円滑な遺産相続を望むなら、相続に詳しい弁護士に早めに相談しておきましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年11月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月15日
- 遺産相続
-
- 2024年06月13日
- 遺産相続
-
- 2024年05月10日
- 遺産相続