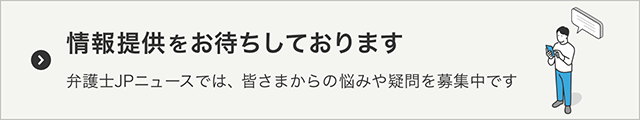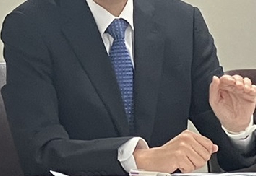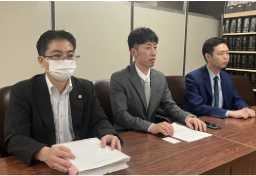テレビ局前社長の退任慰労金減額めぐる訴訟、訴えられた局側は「民法・会社法の解釈に誤り」と主張

テレビ宮崎(UMK)の前社長の渡邊道徳氏が退任慰労金を不当に減額されたとして、UMK側に全額支払いを求めた訴訟で、上告審の口頭弁論が13日、最高裁で開かれた。
渡邊氏は社長在任中、社内規定を超える宿泊費を会社に支出させていたことが発覚。税務当局により超過分を役員報酬と認定されると、負担すべき源泉徴収額をUMKに転嫁し、さらには取締役会に諮ることなく自身の報酬額を増額することで、社内規制に反した宿泊費の支給を実質的に永続化していた。
このことを受け、UMK側は渡邊氏の退職慰労金を3億7720万円から5700万円に減額。これに対し、渡邊氏側は減額を不服とし、UMK側を提訴し、減額分と弁護士費用の支払いを求めていた。
一審・二審では渡邊氏側が全面勝訴も、判断覆る可能性
2021年の宮崎地裁判決では渡邊氏側が全面勝訴。UMK側に2億350万円の支払いを命じており、2022年の福岡高裁宮崎支部判決でも一審判決をほぼそのまま引用する形で、UMK側の控訴を棄却していた。
しかし、今年4月、最高裁が上告受理を決定。上告審の口頭弁論は二審の判決を変更する際に必要な手続きであり、今回の口頭弁論を踏まえ、最高裁判決でこれまでの判断が覆る可能性がある。
13日の口頭弁論の後、UMK側の代理人は都内で報道陣に対し、これまでの経緯や争点について解説。
代理人の池田裕彦弁護士はまず、渡邊氏の退職慰労金の減額を決定したプロセスについて説明した。
渡邊氏は、無断で報酬を増額したことが新聞など報じられた事をうけ、2017年5月、代表取締役社長と取締役を退任することを表明。
その後、UMKの定時株主総会は、在任中「特に重大な損害を与えたもの」について慰労金を減額することができるとした内規に従い、渡邊氏の退職慰労金額を決定するよう取締役会に委任する議案を承認・可決した。
これを受け、取締役会は渡邊氏への適切な支給額を調査するため、外部弁護士3人を含めた調査委員会を設置。
調査委員会は2017年12月、
①渡邊氏の行為は外形的に特別背任罪の犯罪成立要件の充足を否定しきれない悪質な行為である
②取締役会が渡邊氏を刑事告訴することは可能であり、刑事告訴する場合は渡邊氏には退職慰労金の支給を受ける法的期待権はなく、退職慰労金を支給しない手続きをすべきである ③取締役会が刑事告訴しない場合、社会常識の範囲内で、調査委員会が認定した減額可能額を控除した金額を支給することも許されるとした、最終報告書を提出していた。
この最終報告書を受け、取締役会は渡邊氏を刑事告訴せず、5700万円を支給する決議をし、2018年3月に渡邊氏に支給。
ところが、2020年に渡邊氏側が取締役会の判断を不服として、UMKとUMKの寺村明之社長を相手取り訴訟を提起していた。
最終報告書で調査委員会は、渡邊氏による『過大なCSR費用等の支出分』について減額可能と判断したのに対し、渡邊氏側は支出は「特に重大な損害」にあたらず、減額可能とした調査委員会の見解は誤りであると主張した。
原判決「民法・会社法の解釈に誤り」と主張
池田弁護士は続けて、本件での主要な争点について説明。
一つ目の争点はUMKの取締役会による一連の決定は株主総会から与えられた裁量を逸脱・濫用したものかというものである。
一審判決と原判決では、退職慰労金の減額は「重大な損害を与えた」場合にのみ認められているものであり、「CSR費用等の過大な支出」分を減額できるとした調査委員会の見解は誤りであると判断。誤った見解を前提に金額を決定した取締役会は株主総会に与えられた最小を逸脱・濫用したと結論づけていた。
また、二つ目の争点は寺村社長に株主総会決議の委任の範囲や、慰労金内規の解釈適用を誤った過失があるか、というものである。
これについても、これまでの判決では、取締役は調査委員会の見解が誤りでないか独自に判断すべきであり、寺村社長は委任の範囲や、解釈適用を誤った過失があると判断されていた。
池田弁護士は続けて、これらの争点に対するUMK側の主張について説明。
「退職慰労金を含む、取締役報酬の決定は性質上『高度な経営判断』を含むものであり、取締役会には支給の有無や、支給金額の決定について広範な裁量が認められます。
そのうえで、内規に記されている減額の要件については『特に重大な損害』としている以上に、制約を定めているものではないので、退職慰労金についての取締役会の決定が裁量の範囲内かどうかについては、取締役会に広範な裁量が認められていることを前提に判断される必要があります。
ところが、原判決は取締役会の裁量を非常に狭く解釈したものであり、誤っています」
続けて、2つ目の争点についても「取締役会が株主総会から与えられた裁量を逸脱・濫用したものではない以上、寺村社長の過失が問題になることはない」としたうえで、次のように加えた。
「取締役が取締役報酬やその他の経営判断について、専門家の知見を信頼した場合には、その専門家の能力を超えると疑わせるような事情があった場合を除いて、その信頼は保護され、事後的にその判断が誤りであっても過失の評価を受けないという『信頼の原則』が一般的にあります。
にもかかわらず原判決では、調査委員会の調査方法等に不適切な点がなく、専門家の能力を超えると疑わせるような事情が見当たらないのに、『寺村社長は調査委員会の見解が誤りでないか、独自に判断すべきであった』としていました。
こうした点において、原判決には民法・会社法の解釈に誤りがあります」
この日の口頭弁論をもって裁判は結審。7月8日に判決が言い渡される。
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
関連ニュース
-
“国籍”に基づく「レイシャルハラスメント」裁判で原告側が敗訴 “日韓関係”に関する発言、解雇理由や守秘義務が争点に
2024年06月27日 19:01
-
午前2時に部屋に入られ“うなり声”を上げながらの叱責も… 犬の「ブリーディング会社」に対し、元“住み込み従業員”が損害賠償を請求
2024年06月18日 18:32
-
7月から山梨県が富士山“登山規制”を実施 知事「このままでは世界遺産登録が取り消されるおそれもある」
2024年06月17日 19:07