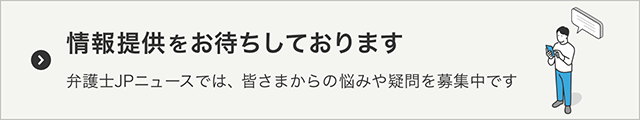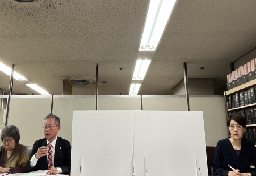上司への突き上げも「パワハラ」認定される!? 部下が発しがちな“あの言動”もアウトの可能性

「見た目通りポンコツ」「給料泥棒」「下級の下級のくず以下」、「お前!」「判断できんやろ」
最初の3つは、奈良県の土木事務所に勤める部下が上司に対し、LINEやショートメッセージで送った文言、次の2つは、兵庫県警の40代男性警部補が、60代の男性警部補に発した言葉だ。それぞれ5月末、6月上旬に発覚したが、共通するのは”逆パワハラ”ということだ。
奈良県のケースでは、処分は減給2か月の懲戒処分、兵庫県警のケースでは、警部補が警務部長訓戒の処分とされた。
厳密にはパワハラに「逆」はない
逆パワハラは、部下から上司に対するパワハラのことで、たとえば、部下が上司に対し、圧力かけて追い込む行為をいう。ただし、パワハラの厳密な定義に沿えば、「逆パワハラ」という言葉は存在しない。なぜなら、そもそもパワハラは、必ずしも上司がその立場を利用して、部下を追い込むことのみに限られていないからだ。
たしかに、職場においては、いまだ職務上の上下関係が重視され、絶対とはいわないまでも、あらゆる場面において「上司の命令には従うべき」という風潮が強固だ。それゆえに、「パワハラ=上司から部下」という印象が強い。しかし、これは大いなる誤解といえる。
キーワードは「職場における優越的な関係を背景とした言動」
「上司の命令には従うべき」という風潮の影響もあるのだろうか。特に言動が激しく感じられた奈良県の事例に対するネット上のコメントは、多くが「処分が軽すぎる」というものだった。このような認識は適切なものといえるか。労働問題に詳しい辻󠄀本奈保弁護士に、”逆パワハラ”の正しい捉え方について聞いた。
奈良と兵庫の事件では、部下が上司に暴言や誹謗中傷の言葉を送り、逆パワハラとして処分を受けています。
辻󠄀本弁護士:部下からのパワハラというと違和感がある人もいるかもしれませんが、厚労省の指針をみれば、上司から部下に対するものだけがパワハラでないことは明確です。キーワードは「職場における優越的な関係を背景とした言動」です。
最もわかりやすいのは職務上の地位が上位の者による言動、つまり上司から部下への”圧”ですね。しかし、これだけでなく、指針には「同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの」ということも記載されています。
これなどは昨今、中途採用でとくにIT系の技術職などでは、知識面で部下が上司を上回るケースも珍しくありません。そうした関係性において、部下から上司に、例えば「こんなことも分からないんですか」といったことを繰り返し発言すればパワハラになり得るということです。
職場でよくありそうな光景という印象です。
辻󠄀本弁護士:ほかにも 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるものというのもあります。これは、部下が集団で上司に反抗的な対応をするようなケースにあたります。
部下が発しがちなアノ言葉が「アウト」になる可能性も
これも結構ある気がします
辻󠄀本弁護士:こういったことが多発しているのだとすれば、それは部下側が、「下からだとパワハラにならない」と誤解している人がそれなりいるからかもしれません。もちろんここまで述べたようにそんなことはありません。むしろ、たとえば、上司の発言に少し圧のようなものを感じ、「それってパワハラじゃないですか?」と切り返して指示に従わなかったりしたら、その発言がパワハラになり得るんですよ。
それはちょっと厳しいのでは…
辻󠄀本弁護士:もちろん一度だけでそう判断されることはあまりありません。上司の発言に対し、頻繁にそうした発言をしていると、パワハラと認定される可能性があるということです。上司もパワハラはいけないということを重々認識し、そうならないよう部下との関係性に苦慮していると思われますから。自身の発言に対して部下から「それってパワハラじゃないですか?」と切り返されるのは、想像以上にズシリときているはずです。
上司部下間のパワハラ格差とは
パワハラにはまだ誤解も多そうです。ネット上では冒頭の事件に対し、「罰が軽いのでは」との声も多くみられました。上司から部下へのパワハラの方が処分は重くなるという判断はあるのでしょうか。
辻󠄀本弁護士:今回は懲戒処分の話になりますが、これまで説明したように、パワハラが認定されたらそこに、上司からか部下からか、という点だけで処分の軽重の差があるものではありません。ただ、上司からのパワハラの場合、その関係性の認定ハードルが低いとはいえるでしょう。上司と部下という関係性はすぐに証明できますから。
一方で、部下から上司へのパワハラだと、どういう点で上司より優越的な関係性なのかを証明するのは簡単ではありません。その意味では処分の軽重に差はないといっても、責任を問われやすい傾向にあるとはいえるかもしれません。
上からはもちろん、下からでもパワハラがある職場というのは本当に「就業環境が害された」ムードが充満します。
辻󠄀本弁護士:上司側がパワハラに苦しんでいる場合、もしかすると相談しづらいとすれば、やはり、組織として第三者的な相談窓口を設けるというのは、ひとつの打開策になり得ると思います。
もちろん、当事者同士はたとえ処分して問題が解決したとしても引き続き同じ部署で働かせるのは合理的といえないでしょう。
結局のところ、パワハラも職場における人間関係に起因することになるので、理想をいえば、コミュニケーションの取りやすい雰囲気や仕組みづくりを意識しつつ、各自がより働きやすい職場になるよう、周囲への配慮も忘れないことが大切になるのではないでしょうか。
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
関連ニュース
-
「気に入らない党員のカジュアル除名横行」除籍・解雇になった共産党員が党を提訴 代理人「結社の自由にも限度ある」
2024年11月13日 16:36
-
「女性から触ってきたから…」セクハラ告発され“降格処分” 不服を訴えるも裁判所から一蹴…男性課長の“悲しき勘違い”
2024年10月28日 09:58
-
“障害者芸術の重鎮”がセクハラなど130もの不法行為、裁判でおおむね事実と認定 社会福祉法人の元理事長らに計660万円の賠償命令
2024年10月25日 13:50