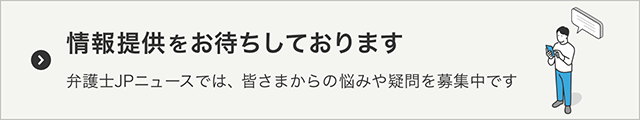子どもの性被害防ぐ「日本版DBS法」成立も…立ちふさがる3つの“ハードル”

保育園や学校など子どもたちと接する職場への就職希望者の性犯罪歴を開示する日本版DBS(Disclosure and Barring Service、ディスクロージャー・アンド・バーリング・サービス=前歴開示および前歴者就業制限機構=)の創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法」(日本版DBS法)が6月19日、参議院本会議を通過し、可決・成立した。
これを受け同日、いち早く日本版DBSの設置を訴えてきたNPO法人フローレンス(本部・東京都千代田区)の赤坂緑代表理事らが厚生労働省で記者会見を開き、制度の充実などを訴えた。
8万筆の署名集め創設機運一気に高める
東京都目黒区のマンションで2020年6月、ベビーシッターの男性(当時30歳)が5歳の女児の身体を触るなどしていた行為が発覚。日本でのDBS導入が検討され始めた。
DBSは、イギリス他欧州数か国で採用されている性犯罪歴の開示制度。子どもに関わる職種で働くことを希望する求職者は、DBSから発行される犯罪証明書が必要となっている。事業者は採用の際に、この証明書の確認が義務づけられており、性犯罪歴がある人物の採用を未然に防ぐ制度となっている。
日本版DBSは、事業者側が、従業員・求職者の性犯罪歴の有無を、こども家庭庁を通じて法務省に照会・確認を義務づける(民間の学習塾などは任意の認定制)。今後、制度の詳細を決定し2年半以内(2026年12月まで)に施行、施行から3年で見直しが行われる。
記者会見を行ったフローレンスは2004年設立。子どもと子育て領域の社会課題解決に取り組み、子どもの性被害にも警鐘を鳴らしてきた。前述した目黒区での事件直後にはソーシャルアクション「#保育教育現場の性犯罪をゼロに」を開始。日本版DBS創設を訴えてきた。23年8月には緊急署名活動を行い、8万筆を超える署名を集め、小倉將信こども政策担当大臣(当時)に提出。創設への機運を一気に高めた。
記者会見には、同法人の赤坂代表理事と学習塾「花まる学習会」の高濱正伸代表、末冨芳氏(日本大学文理学部教育学科教授)、中野円佳氏(東京大学多様性包摂共創センター准教授)の4人が臨んだ。
小児性犯罪で有罪が確定する者はごく一部

赤坂代表理事はこれまでの活動の経緯とともに、「(日本版DBS法が)成立したことは大きな一歩ではあるが、まだまだ100点満点とは言えない。改善すべき点が多くあり、引き続き議論していく必要がある」と語った。
さらに改善すべき点として、具体的に以下3点を示し説明を行った。
①照会の対象となる性犯罪歴の範囲
②性犯罪歴を照会できる期間
③認定制度
「照会の対象となる性犯罪の範囲」は現在、刑法・条例に違反する行為(子どもに対する性的行為、痴漢等)で有罪判決を受けた者(前科者)のみが対象となっているが、赤坂代表理事は「小児性犯罪で有罪が確定する者はごく一部で、不起訴処分(起訴猶予)、懲戒処分にしかならないケースが多く、前科だけでなく起訴猶予等も(照会の)対象とすることを検討していただきたい」と要望した。
「性犯罪歴を照会できる期間」については、「子どもへの性犯罪は再犯の可能性が非常に高い」(赤坂代表理事)とし、現在の最長20年を見直し、より長い期間の紹介を可能にするよう求めた。
「認定制度」とは、求められる措置(教員等の研修など)を取った塾や学童教育、ベビーシッターには日本版DBS法に準じている「認定」が与えられる制度のことだが、中小事業者の場合は、「認定」を取りたくても教員等への研修実施のハードルが高くて取れないことが考えられる。
その結果、「認定を取っていない施設に加害歴のある人が流れ込み、抜け道ができてしまう。(それを防ぐために)認定を取りやすいよう(中小事業者を)支援する仕組みをつくっていく必要がある」(同代表理事)。
「性加害者は現場では全く分からない」
30年以上にわたって学習塾経営にあたってきた高濱代表は、現場の“苦悩”も語った。
「性加害を起こすか起こさないかは現場では全く分からない。IQも高く、柔和な人格者だと思っていた人物が、そんなことをするのか、ということもあった。(小児性愛の)性癖のある人物が違う場所(施設)に移動していることも少なくない」
中野准教授は加害者の性的特性に触れ、「小児性犯罪は依存症のようなところがあり、子どもがいる環境にいれば再犯の可能性が高まる。ほかの仕事に就いてもらうことは大事だと思う」と語った。
末冨教授は、児童相談所と警察など、対応機関が細かく分かれていることに触れ、「イギリスは子どもに関わるリスクは一元化して防止していこうとしている。(日本も)あらゆる場面で子どもたちが守られるより大きな仕組みをつくっていく必要がある」と述べた。
「子ども守るために大人の責任問われている」
12歳以下の子どもが被害者となる性犯罪は年間約1000件――。
この数字だけでも衝撃的だが、「この数字は氷山の一角とも言われている」(赤坂代表理事)という。
性被害に遭ったときにそれを「被害」だと認識できた割合は52%で、子どもたちが何をされたか分からないケースも少なくない。1年ほど経った後で、「そういえばこういうことをされた」などと親に伝えることもあるという。
見えない数字の中に、身近な子ども、自分の子どもが含まれることがあるかもしれない。自らも小学生2人の母親でもある赤坂代表理事は、会見の最後に力を込めて語った。
「全ての子どもと関わる人たちに認識を新たにしてほしい。真に子供たちを守るためにどうすればいいか。大人の責任が問われている。多くの方に関心をもっていただきたい」
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
おすすめ記事