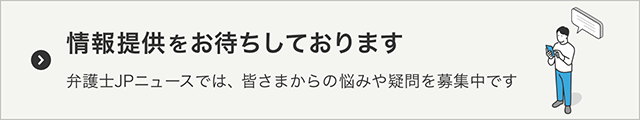“国籍”に基づく「レイシャルハラスメント」裁判で原告側が敗訴 “日韓関係”に関する発言、解雇理由や守秘義務が争点に
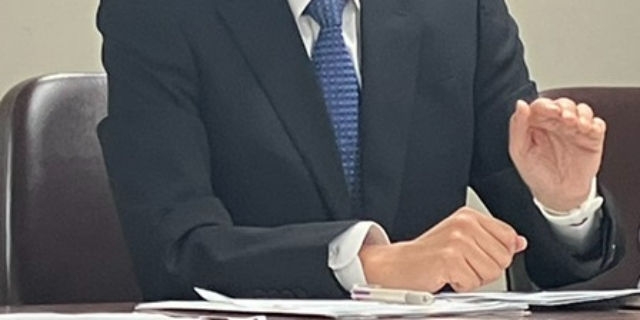
6月27日、上司からのレイシャルハラスメント(人種・国籍に基づくハラスメント)被害を申告したことが原因で解雇されたとして、証券会社に勤務していた男性が会社側を訴えた裁判で、東京地裁は原告の請求を棄却する判決を出した。
訴訟の概要
原告は韓国籍の40代男性。モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社のエグゼクティブ・ディレクターとして勤務していた。
男性は2012年頃から度重なるレイシャルハラスメント被害を上司から受けていたとして、2020年3月に会社にハラスメント被害を申告。しかし、会社側が調査を行った後にハラスメント該当性を否定した。
同年7月、米国本社と日本法人の経営陣らへ、会社側の対応についての問題を指摘するメールを送信したことなどを理由に、男性は自宅待機を命じられる。その後も同様のメールを送信したところ、9月に懲戒処分(けん責処分)を出され、2021年1月に解雇を通知される。その後同年2月末、男性は解雇された。
被告は、男性と雇用関係にあるモルガン・スタンレー・グループ株式会社。
原告は解雇無効、懲戒処分の無効確認、賞与の支払いなどのほか、ハラスメントの調査義務違反などを理由とする損害賠償を請求した。
日韓関係の問題が起こるたび批判される
原告側によると、男性の上司は日韓関係に関した問題が生じるたびに、勤務中の男性に対して韓国を批判したり、男性のことを責めたりする言動を行ったという。
以下は、レイシャルハラスメントにあたると原告が訴えている、上司の発言の例。
・2012年、イ・ミョンバク大統領が天皇に対して謝罪を求める発言をした際に「天皇を侮辱するな」
・2014年、田母神俊雄氏が都知事選に出馬した際に「田母神氏じゃなかったらどのように東京を中国人と韓国人から守ることができるんだ」
・2018年、元徴用工に関する韓国大法院判決が出た後に「日本が韓国に多くの資産とインフラを残してきたので、本来であれば韓国が日本に賠償をしなければならない」
・2019年、韓国海軍が海上自衛隊の哨戒機にレーダーを照射した事件に関して「どうにかしてくれ、君の先輩だろ」
これらの発言があったことについては、被告側も「不適切な言動はあった」と認めている。しかし、発言の際に上司の口調は平穏であったこと、そして発言の頻度も少ないことなどを理由に、被告側は「ハラスメントにはあたらない」と主張した。
今回の判決ではこうした被告側の主張を受け入れ、上司の発言は「原告に不快感を与える行為であり、精神的苦痛を与える行為」と認定しながらも、ハラスメントには該当しないと判断した。
守秘義務や解雇理由も争点に
原告側は、男性の申告を受けて会社が行った調査は申し立てた内容とは異なる事実を調査対象としており、目撃者として伝えた10名のうち2名のみを調査するなど、調査の方法に問題があったと主張。
また、被告側は、調査開始時に男性が署名した秘密保持契約を理由に、男性には守秘義務があると主張。
判決でも、被告の主張を認めて、守秘義務は調査が終わった後も無期限に続くこと、調査の内容のみならず被害の事実も守秘の対象になること、さらに調査結果に対する意義を社内で述べること自体が懲戒理由にあたると認定された。
判決後の会見で、男性は「守秘義務の範囲が広すぎるし、期間が無限というのもあり得ない。会社の主張が裁判所に追認されたのは残念だ」と語った。
裁判所は、男性が会社を誹謗中傷したり業務を妨害したりするおそれがあることを認定して、解雇理由も妥当であると判断。
これに対して、原告側は、けん責処分が行われた2020年9月以降、男性は取引先へのメールの送信や業務を妨害する行為を行っていないのに、4か月後に解雇を通知されたことは不当であると主張。「主観的な“おそれ”を理由に解雇を正当化した」と、裁判所の判断を批判した。
「総じて、会社の言い分をそのまま追認する不当極まりない判決であり、断固抗議する。
原告、弁護団および支える会は、不当判決に対し、直ちに控訴し、断固としてたたかう所存である」(判決後の声明から)
レイシャルハラスメントには厳しい対応が必要か
会見で原告側の弁護士たちが主張したのは、本人の意思で変えることができない「国籍」や「人種」に基づくレイシャルハラスメントには、通常のパワーハラスメントよりも厳しい対応がなされるべきということだ。
「発言の口調や頻度がハラスメント認定に関わる場合も、たしかにある。しかし、男性の上司が発言した内容は、どんな状況でも許されないものだ」(加藤健次弁護士)
青瀧美和子弁護士も、判決で厚労省によるパワーハラスメントの定義が挙げられたことに関して、今回の事件に対して通常のパワハラの基準を当てはめるのは適切でないと批判。
男性は「私は協調性が欠けているわけではなく、能力不足でもなく、会社に損害も与えていない」と悔しさをにじませながら語った。
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
関連ニュース
-
「パワハラというには生ぬるい、過酷な仕打ち」従業員が会社に損害賠償を請求 屋外の“お立ち台”、 “追い出し部屋”の学習などで「さらしもの」
2024年12月26日 15:20
-
「ハラスメントのない職場環境を」生協のスーパーでパート女性自死、和解成立で遺族側が会見
2024年12月26日 13:33
-
現役自衛官セクハラ訴訟 公益通報後に「二次被害」「昇任までに12年」“不利益取り扱い”か
2024年12月24日 15:36