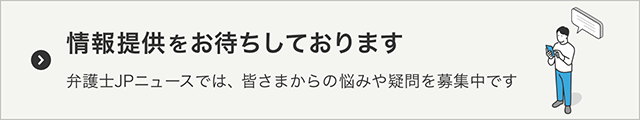食べログに「独禁法違反」も…アルゴリズムは“黒塗り”のワケ

食べログで行われたアルゴリズムの変更が独占禁止法違反(優越的地位の濫用)にあたるとして、運営会社のカカクコムに3840万円の賠償を命じる裁判判決が6月16日に言い渡された。
「チェーン店であることを理由に評価を不当に下げられた」としてカカクコムを訴えていた焼き肉チェーン「KollaBo(コラボ)」の運営会社・韓流村が勝訴した一方、韓流村が求めていた「変更後のアルゴリズムの差し止め」については命令が下されなかった。また、裁判資料の一部には閲覧制限が掛けられており、アルゴリズムの変更内容や、アルゴリズムを変更した理由については、当事者にのみ明かされた状態となっている。
「飲食店に無断で掲載」問題ない?
食事するお店を選ぶ際に「食べログ」などの飲食店ポータルサイトを参考にしている人は多いだろう。一般的に飲食店ポータルサイトでは、ユーザーによって投稿された評価とアルゴリズムを組み合わせることで、掲載店舗の評価(評点)を導き出している。2020年に公正取引委員会が公表した「飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査について」によると、ユーザーの約83%がこの評価(評点)を参考にしていると回答した。
また飲食店ポータルサイトは、飲食店側にも大きな影響をもたらしている。前出の調査では「予約の過半数を特定の飲食店ポータルサイトに頼っている」「新規の来店客のほとんどは飲食店ポータルサイト経由」といった恩恵を受ける声が聞かれた。
その一方「(飲食店ポータルサイトに)無断で掲載され不利益を被った」と回答した飲食店も約29%あった。そのうち約54%は削除・修正を求めたものの、少なくとも約29%は応じてもらえていないと回答している。
店舗情報や、それに紐づく評価、口コミについては、食べログなどのように飲食店側の意思にかかわらず掲載されるケースも多い。これについて公正取引委員会は「飲食店からの依頼に応じて修正・削除しないことが直ちに独占禁止法違反となるものではない」との見解を示している。
「もっとも知りたい部分はブラックボックス」
飲食店ポータルサイトに限らず、評価サイトやニュースサイト、検索エンジンなど、今やアルゴリズムは人々の生活に深く浸透している。またビジネスにおいても、アルゴリズムによって利益が大きく左右されることは珍しくなく、その透明化には多くの人が関心を寄せているだろう。
今回の判決がアルゴリズムの透明化に与える影響などについて、企業法務に携わる折田忠仁弁護士に聞いた。
今回の判決ではカカクコムの独占禁止法違反が認められた一方、食べログのアルゴリズムには閲覧制限が掛けられており、当事者以外はその実態を知ることができません。そのような状況にあって、今回の判決は今後、評価サイトなどの公正性や透明化にどのような影響を与えると思いますか?
折田弁護士:本訴訟では、韓流村は、食べログ側がチェーン店の評価を一気に低下させるようなアルゴリズムの変更を行ったことを問題視しました。
判決によれば、食べログと同種の飲食店ポータルサイトが、チェーン店の評価につき、以前の評価を有意に低下させる結果となるようなアルゴリズムの変更をすると、優越的地位の濫用で「違法」と評価される場合があるということになったわけです。
したがって、この判決が確定すれば、そのような行為に歯止めがかかることで、チェーン店の評価における公正性や透明化に寄与する結果になることは間違いないでしょう。
チェーン店が「チェーン店だから」という理由で、非チェーン店より評価が低くなるというのは不合理といわざるを得ません。
ただし、本訴訟においては、食べログ側がアルゴリズムの変更を一部開示するとともに、その主張を記載した書面を数回にわたり提出しています。そこにはアルゴリズムの変更内容と、なぜそのようなアルゴリズムの変更を行ったのかが記載されているはずです。
しかし、閲覧制限がかかっているので、我々が最も知りたい部分はブラックボックスになってしまっています。つまり、食べログ側は、閲覧制限を行った箇所において、自分たちが実施したアルゴリズムの変更は、優越的地位の濫用に該当するような違法行為ではないことを詳細に説明しているはずで、我々実務家としては、そこを知りたいわけです。
食べログ側が主張した理由は退けられたけれども、それは何かが足りなかったからなのか、他の理由なら優越的地位の濫用に該当しない余地があるのか、どのような理由があろうとも優越的地位の濫用になってしまうのか…。その点の研究・解明が進められないと、すべてがクリアになったとはいえないでしょう。
判決では、食べログ側の「優越的地位の濫用」は認められたものの、原告・韓流村が求めた「変更後のアルゴリズムの差し止め」命令は下されていません。その理由についてはどのようにお考えでしょうか。
折田弁護士:独占禁止法第24条に基づき、独占禁止法違反行為(不公正な取引方法に係るもの)によって著しい損害を受け、または受けるおそれがある者は、裁判所に当該行為の差止めを請求することができます。優越的地位の濫用は、不公正な取引方法のカテゴリーに入りますので、韓流村は、同条に基づいて差止請求をしたと考えられます。
裁判所は、食べログ側の優越的地位の濫用という違法行為を認めながら、その差止めは認めませんでしたが、それは差止めをするほどの必要はないと判断したからでしょう。
食べログ側は、韓流村のみを狙い撃ちしたわけではありませんから、そのアルゴリズムの変更は、チェーン店を展開している事業者全体にマイナスの影響を及ぼしたはずです。しかしながら、訴訟を起こしたのは韓流村だけであったことからすると、チェーン店を展開している事業者全体に深刻な悪影響を及ぼすような変更なのかという疑問が生じますし、差止めまで認めなくとも損害賠償による救済で足りるのではないかとも考えられます。
この点については、韓流村は勝訴後、同業者に訴訟への参加を呼び掛けていますので(※1)、どのくらいの参加者が集まるかによって、結論に影響が出るかもしれないと注目しています。
(※1)韓流村は「食べログ被害者の会」を立ち上げ同業者に訴訟への参加を呼び掛けている
今回のように、裁判資料へ「閲覧制限」が掛けられることはよくあるのでしょうか?
折田弁護士:そのとおりです。閲覧制限は、「訴訟記録中に当事者の私生活上の重大な秘密、当事者が保有する営業秘密等が記載又は記録されている場合」に可能であり(民訴法第92条1項)、広く行われています。
私が最近経験したケースでは、相手方は、当事務所の依頼者企業に対し、自社の営業秘密を不正に使用しているとして、当該不正使用の差止めを求めるとともに、自社の営業秘密を記載した書面の閲覧制限を申立てたのですが、裁判所は、その申立てを認めました。
しかしながら、我々は、相手方が主張する営業秘密なるものは営業秘密としての要件を充たさないとして争い、その結果、裁判所は、我々の主張を認め、相手方には営業秘密といえるものはないという決定をしました。
これを見ても、裁判所は、閲覧制限の申立てを認めるにあたって、それほど厳密には判断しておらず、営業秘密に該当する可能性があれば、基本的には閲覧制限を認めているという印象です。
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。